
じゅんジュンJUNちゃん闘病記別館

この文章はもともと専門家に向けて書いていますので,一般の方には少し難しいかもしれません。
米国の小児脳腫瘍基金によれば,小児の脳腫瘍は小児がんの中で最も死亡率が高くて,34才までの癌死の最も大きな原因になりつつあるということです。でもこの事実は日本ではあまり知られていません。腫瘍ができる臓器別でみれば,日本でも小児に発生する固形癌の中では脳腫瘍は最も頻度が高くて,白血病による死亡率の低下とともに15才未満の癌死の中では脳腫瘍が最大の原因と考えられます。
しかし,小児脳腫瘍の正確な統計はとられていませんし,いま日本でそれを知る手段はありません。髄芽腫は,小児の悪性脳腫瘍として最も有名です。髄芽腫の年間発生率は10万人あたり0.06-0.07人くらいでしょうから,発生数は全国で1年あたり80例ほどと推定されます。髄芽腫は15歳未満の小児脳腫瘍の約10%を占めるので,小児脳腫瘍の発生率は人口10万あたり年間1人弱なのかもしれません。
後で述べるように小児脳腫瘍の治療の選択肢はとても複雑ですから,髄芽腫においてさえも患者さんの家族が単純に判断できて選べる標準的治療というものがありません。ですから小児脳腫瘍の治療方針という問題を簡単に書くことはできませんが,良性腫瘍の治療も含めて,最新の治療指針とは何かを考えるための参考となることを記載します。
他の臓器に発生する小児の腫瘍と比べたとき,小児の脳腫瘍の最大の特徴は,病理組織が実に多彩なことです。日本脳腫瘍統計による14歳以下の脳腫瘍の病理組織型別頻度は,星細胞腫が19%で,髄芽腫(11.9%),胚腫(ジャーミノーマ)(9.5%),頭蓋咽頭腫(8.9%),退形成性星細胞腫(5.7%),上衣腫(4.5%),膠芽腫(3.5%)などが続きます。
その他の脳腫瘍の頻度はとても低くてまれなものになります。上記以外で放射線や化学療法を用いるものに,テント上原始神経外胚葉性腫瘍(PNET),脳幹部びまん性星細胞腫,毛様細胞性星細胞腫,退形成性乏突起膠腫,乏突起膠腫,退形成性乏突起星細胞腫,乏突起星細胞腫,退形成性上衣腫,胎児性癌,未熟奇形腫,悪性奇形腫,混合性胚細胞腫瘍,卵黄嚢腫,絨毛上皮癌,中枢神経原発リンパ腫(PCNSL),松果体芽腫,大脳神経芽腫,嗅神経芽腫,脈絡叢乳頭癌,非定型奇形腫様/ラブドイド腫瘍(AT/RT),悪性末梢神経鞘腫(MPNST),軟骨肉腫,髄膜黒色腫などがあります。
手術摘出が主として行われる小児腫瘍に,各種機能性腺腫を含む下垂体腺腫,シュワン細胞腫(神経鞘腫),神経線維腫,髄膜腫,血管芽腫,海綿状血管腫,ラトケ嚢胞,類表皮嚢胞,類皮嚢胞,成熟奇形腫,松果体細胞腫,上衣下巨細胞性星細胞腫,上衣下腫,脈絡叢乳頭腫,中枢性神経細胞腫,神経節細胞腫,小脳異形成性神経節細胞腫,神経節膠腫,胚芽異形成性神経上皮腫瘍(DNT),線維形成性乳児神経節膠腫(DIG),血管外皮腫,脊索腫,骨腫,軟骨腫,線維性異形成症,第3脳室コロイド嚢胞,松果体嚢胞,視床下部過誤腫,異所性灰白質,脂肪腫、NF-1とNF-2関連過誤腫などがありますが,さらに細分類をすれば限りがありません。
ですから小児の脳腫瘍を治療する医師は,これらの全てを理解していなければならないので,途方もない知識を求められます。例えば小児の白血病の治療ができるからといって小児の脳腫瘍の治療ができるとは限りませんし、脳腫瘍の手術が上手だからといって脳腫瘍の化学(薬物)療法がわかるとはいえません。小児脳腫瘍にとても詳しい先生に巡り会えるかどうかが重要になります。
ちなみに私は,AT/RTを除けば上に書いた全ての小児脳腫瘍を治療した経験がありますが,それぞれの組織型を数多く見ている訳ではありません。現実には患児が来るたびに有する組織型が変わり,例えば乏突起神経膠腫の患児の次は星細胞腫,その後に神経節膠腫などといった具合です。これらの神経膠腫と呼ばれる腫瘍は,症候性てんかんなどとてもよく似た症状で発症して,MRI画像所見もとても似ていますが、それぞれの治療法は異なっているので,初診時の画像所見を診誤れば,治療計画全体にあやまりを生じて治す機会を失ってしまうこともあります。
手術をするかどうかを含めて、はじめて治療を決めるときの初期判断が最終的な予後を決めてしまうといっても言い過ぎではありません。もう一つ決定的に重要な診断は病理診断です。しかし,経験を積んだ病理診断医でも星細胞腫と乏突起膠腫の鑑別には困ってしまうことがあるくらいです。小児の脳腫瘍の治療方法の選択は限りなく複雑なのです。
日本脳腫瘍統計によれば,1991年以降に登録された上衣腫の5年生存率は73%であって,頭蓋咽頭腫は91%です。これらは良性腫瘍とされるものですが,上衣腫では4分の1が5年以内に死亡することとなりますし,頭蓋咽頭腫においては手術の数ヶ月から数年後の再発や再燃も多くて,何度も手術を受けたり,大きな後遺症をかかえて生存する子供たちも多いのです。
頭蓋咽頭腫は,視床下部と神経下垂体という脳の深くて重要な機能をもつところにできて,そこにくっついているために,熟練した脳神経外科医にとっても手術がとても難しいので,統計に載らないところでの手術死亡例も少なくないと想像されます。また頭蓋咽頭腫の手術ではできる限り下垂体の機能を守ることを考えますが,現実には間脳下垂体機能不全症と視力視野障害を残して生存する例が大多数です。さらに手術で完全摘出できないとき、とくに小さな子供たちに放射線治療おこなえば精神発達遅滞の可能性が残ります。
他にも良性脳腫瘍といわれる例を挙げれば,海綿状血管腫や神経節膠腫などが中脳に発生してゆっくり大きくなった時には,有効な治療法はほとんどなくて生き残る機会は少ないといえます。このように病理組織学的に良性といわれる脳腫瘍でも,少なからず重篤な内分泌不全や神経脱落症状(後遺症)を残しますし,かつ子供たちを死に導く可能性のある病気です。多くの脳腫瘍において教科書に書かれている組織学的な良性度というのは必ずしも治りやすいということを示しません。良性というべき生易しいものはほとんどないのです。
日本脳腫瘍統計によれば星細胞腫(WHO grade 2)全体の5年生存率は66%ですが,一方で脳幹部に発生した星細胞腫の死亡率はほぼ100%です。この様にびまん性星細胞腫(diffuse astrocytoma, WHO grade 2)と診断される腫瘍はできる場所によって生命予後に大きな開きがあります。
さらに例を挙げれば,右前頭葉の前の方に発生した同じgrade 2の星細胞腫でも,類円状で限局性に発育する(固まりになっている)ものとグリオマトーシスのように強い浸潤性格(しみ込むように広がっている)を示すものでは予後は異なります。前者は完全手術摘出のみで治癒しますが,後者は生検術と放射線治療を行っても治ることはほとんどありません。
小脳に発生した星細胞腫(grade 1 & 2)では,32%に増殖停止(大きくならないでそのままいること)が14%に自然退縮(何もしないでも腫瘍が小さくなる)が生じるという報告もありますから,手術の後で取り残した腫瘍があっても何もしないでそのまま様子を見た方がいいこともあるのです。これらの違いは,組織学的な診断(病名)が同じであっても発生した脳の場所によってそれぞれ治療法を変えなければならないということを示しています。
欧米の1000例を越えるランダム化臨床試験では,成人のテント上星細胞腫への放射線治療の有効性(生存期間の延長)は証明されませんでした。従ってエビデンス・レベル1(科学的にしっかりした事実)でテント上星細胞腫への放射線治療の適応はありません。腫瘍学の常識では同じ組織型であれば放射線治療の効果は同様であるはずなので,小児の星細胞腫へ放射線治療をしても効かないと考えられます。加えて高いエビデンス・レベルをみれば,星細胞腫grade 2に有効な化学療法剤はなくて,結局,予後に最も大きな影響を与える因子は手術できちんと取れたか否かです。
従ってテント上星細胞腫の治療で,理論的に勧められることは完全手術摘出のみであって,腫瘍のできた場所によってのみ治療の適否が決まります。でも脳という臓器はこの単純性を許しません,脳のたいせつな場所をまきこむ星細胞腫の完全摘出を計画することはできませんので,多くの星細胞腫では生検術後に放射線化学療法を用いて治療されます。ここには理論的に正しい治療と実際の治療が全然違うというとても大きな矛盾があります。
脳腫瘍の治療後遺症として知能の発達は大きな問題です。成人の喪失性の認知障害とは異なり,小児の精神発達遅延あるいはIQ(知能指数)の低下は学習獲得能力の低下によって生じます。少し難しいかもしれませんが,忘れるのではなくて新しいことが学習できないから知能が低下すると考えて下さい。最近では認知障害ということばがよく使われます。
認知障害は,脳白質の発達障害が原因とされます。後遺症を大きくする危険因子として,治療されたときの低い年齢,治療からの経過期間,放射線の線量と範囲と部位、手術摘出の部位,水頭症の存在があります。
発達しつつある乳幼児の脳は放射線治療に対してとても弱くて,特に3才未満の小児の大脳に放射線治療を行えば重度の中枢神経発達障害(重い知能低下)を招く確率が高いのです。また3才になってからも成人と同じ放射線治療ができるわけではありません。
年齢が低ければ放射線量を少なくするように微調整するために,小さい子供には治療に必要な放射線を十分使うことができません。ですから低年齢児ほど放射線治療の代わりの化学療法の役割は大きいのですし,またそれによって治療期間が長期になります。
1990年にHoppe-Hirschという人は,髄芽腫の治療を受けた120人の子供たちを追跡して、治療5年後には42%の患児でIQ(知能指数)は80を下回り,治療10年後には85%の患児でIQは80を下回るというとても恐ろしい結果の報告をしました。
2001年のRisらの報告によれば,23.4Gyの低線量脳脊髄照射によっても知能低下は明らかではあるが,旧来の放射線治療と比較すれば知的機能の温存率は改善の傾向があったとしました。彼らの報告でも,患児のIQは1年あたり4.3低下していって,7歳以下で治療を受けると低下率は著しくて,3年以上経過した15症例の平均FSIQ(知能指数)は75.7であり更に低下の傾向をたどるとされています。さらに最近,5歳以下に脳脊髄18Gyという低い線量も用いられましたが,内分泌機能障害と知能の低下は避けられなかったと報告されました。
放射線治療ばかりが後遺症を大きくする訳ではありません。放射線治療以外の治療方法でも小さな子供たちは障害を強く受けます。低年齢児でのメソトレキセートの髄腔内注入が認知障害を大きくすることも知られていて,よほどの必要性がなければこの化学療法は使用されるべきではありません。でも実際には,髄芽腫の治療でメソトレキセートを使っているグループもあります。
PNETは大脳に発生するので認知障害は小脳に発生する髄芽腫より重くなります。治療を受けて生き延びて何年もたってから起る後遺症としての脳血管障害と二次腫瘍の発生リスクは,これも低年齢児の方が明らかに高くて,脳腫瘍の場合においては放射線治療と関連する遅発性合併症であるといわれます。
全ての小児脳腫瘍は稀少腫瘍(珍しい腫瘍)ですから,統計理論的にはランダム化第II相試験,第III相試験というきちんとした臨床試験を成立させるための登録症例が集められません。そのために確かな事実に基づいた標準プロトコール(治療計画)を作ることが困難なのです。
もちろん,髄芽腫を100例以上あつめて臨床研究ができればよりよい治療の方法が見えてくるのですし,小児脳腫瘍でも設定根拠のある対象集団に対して根拠のある計画治療を行う集学的治療の第II相試験でレベル3の有効性と安全性を検証することは可能でしょう。(ちょっと理解できませんか?) 要するに小児の脳腫瘍研究は大規模にはできないのです。この脳腫瘍の特徴を踏まえて,世界脳腫瘍会議では小児も含めた脳腫瘍の第I相と第II相試験のためのガイドラインを作成中です。
学会でlow-grade glioma(悪性度の低いグリオーマ)の治療という発表を聞くことがあります。ある日本の研究グループに登録された”low-grade glioma”に一定の化学療法を用いて治療した成績の発表などです。でも,このlow-grade gliomaという呼び名は治療方法を検証するために一つに括ることができる設定根拠のある単一対象集団ではありません(違ったものを十葉一絡げにして研究してはいけないという意味です)。だから,このような学会発表には意味がありませんが,学会で発表された成績というと一般の人には本当のことのように思えてしまいます。
逆に病理学的に悪性度の低いグリオーマの治療方針は個々の患者さんにおいて千差万別です。ヘテロな対象集団にヘテロ(個々においては適切)な治療を施すことを許容することが認められなければならない腫瘍に,研究プロトコールに基づいた治療を安易に設定することには危険があります。これは治療方針がきちんと立てられているからといってその治療が正しいということではなくて,逆に一つの方針でおおざっぱにまとめて治療しているから間違っているということです。
小児の脳腫瘍は標準化して治療計画を立てることが難しいし、科学的な画一性を求める臨床研究の発展は小児脳腫瘍の極めて高い多様性との背反の中にあることも逆に認識されなければなりません。一見きちんとした治療方針で治療しているということが,それぞれの子供たちにとっては正しいことではなくて,きめ細かな治療計画がないがしろにされていているということもあるのです。
髄芽腫では高リスク群と標準リスク群でという2つのグループに分けて治療法が選択されます。高リスク群というは「治すのが難しいという意味」で,3歳未満の乳幼児,髄腔内転移の存在,術後の1.5cm2以上の残存腫瘍の存在の一つを含むものと理解されます。例えば2歳の髄芽腫で脊髄転移をしているか手術の後に取り残しがあれば治療がとても厳しいと理解して下さい。手術によって腫瘍が全摘できたかどうかは生命予後を決定する最も大きな要因ですので,可能であれば常に全摘出を目指します。
放射線治療
術後できる限り早い脳脊髄照射の開始を基本とします。2007年時点で標準リスク群に対して基本になるのは,23.4グレイの脳脊髄照射と総線量55.8Gyの後頭窩照射です。3歳以上の患児に対しての照射は1日線量1.8Gy,週5回照射が標準的です。一方、高リスク群には脳脊髄照射35-36Gyが用いられます。最近では,旧来の対向2門照射ではなく3次元治療計画を用いることが多くなっています。
発達過程にある乳幼児の中枢神経は放射線治療に対して著しく耐性が低く脆弱で,特に3才以下の小児に放射線治療を行えば重篤な中枢神経発達障害を招く確率が高いです。しかし,3才になってからも成人と同様の放射線治療ができるわけではなく年齢に正の相関となるように放射線量を調節するために,低年齢児ほど照射線量を下げるため補助化学療法の役割は大きくなります。
化学療法
2006年にPackerらは,3歳から21歳までの標準リスク群髄芽腫379人の無作為化比較大規模臨床試験の結果を報告しました。全摘あるいは亜全摘術後31日以内に放射線治療(23.4Gy全脳脊髄照射,55.8Gy後頭窩照射)が開始され,放射線治療中は毎週ビンクリスチン(1.5mg/m2)の投与がなされ,その後,ロムスチン,シスプラチン,ビンクリスチン併用化学療法あるいはシクロフォスファミド,シスプラチン,ビンクリスチンを使う化学療法のいずれかが,合計8コース加えられたものです。無増悪5年生存割合は81%,全5年生存割合は86%というすばらしい成績を残しました。化学療法の違い(ロムスチンかシクロフォスファミド)では生存割合に差はありません。この報告は,最大規模の無作為化比較臨床試験であり,かつ最も優れた成績を残した故に,今後の標準リスク群髄芽腫での標準治療とされるべきものになったと評価されます。
高リスク群において低線量照射を用いる代表的成績は,23.4Gyの照射とロムスチン,シスプラチン,ビンクリスチンの併用化学療法用いるもので,約65%の5年生存率が得られたとの報告がああります。また,高リスク群の中でも特に3歳未満の症例では,放射線治療を待機するために化学療法が先行して行われることが世界標準になりました。しかし,現在でも様々なプロトコールが模索されているのが現状です。
3歳以下の低年齢層には造血幹細胞救援を併用する大量化学療法の有用性が期待されています。しかしこれも明らかな利点を証明するには至っていませんし,化学療法死を含めた強い副作用と生存期間延長の利害が厳密に比較検討されなければならない時期にあります。カルボプラチン,チオテーパ,エトポシドを用いる地固め療法を21例の高リスク群に用いた研究結果では,無増悪3年生存率が49%であったと報告されました。この研究は髄液播種を伴う低年齢児を多数含んでおり照射を6歳まで待機する方針であるので期待が持てる成果とはいえますが、逆に大量化学療法といえども単独では半数以上に再燃が生じることを示しています。 日本でも一部の施設で行われていますがこれが有効かどうかの長期成績は正式には発表されていません。
澤村は1992年から年齢に応じた18-25Gyの脳脊髄照射とイホスファミド,シスプラチン,エトポシドを併用するICE化学療法を6コース用いる化学療法を併用するプロトコールを用いていますが,高リスク群も含めて治療後追跡期間中央値65ヶ月での5年生存率は70%程度ですから欧米からの報告と大差はないものかもしれません。
髄芽腫でも治りにくさに差があって悪性度はいろいろです。髄芽腫のおよそ4分の1にみられて悪性型と分類される退形成性髄芽腫は高頻度にERBB2という蛋白を作ります。Gajjarらによれば標準リスク群かつERBB2陰性の26例での5年生存率が100%であり,一方ERBB2陽性の13例での5年生存率が54%であったとのことです。この事実が証明されれば近い将来には,標準リスク群の治療強度はERBB2の発現をみることで大きく変わるのでしょう。でもこれにも反対意見もあって分子診断の将来ははっきりしていません。
全般的に小児脳腫瘍の治療研究体制は欧米に遅れていますが,東南アジアでの胚細胞腫瘍の発生頻度は欧米の数倍にあたるために,胚腫(ジャーミノーマ)の治療に関しては日本が欧米をリードしています。厚生労働省の松谷班の研究成果が現時点での日本の標準治療となっていますし,私もこの腫瘍に対してはたくさんの論文を書きました。
胚細胞腫瘍といってもいろいろな腫瘍の集まりですから,病理分類によって適切な治療方針を決めることは難しいです。日本では治療法の選択のために組織型によって,予後良好群,予後中間群,予後不良群の3群に分類しておよその目安としています。
予後良好群は胚腫と成熟奇形腫です。80-90%の10年生存割合が期待できる群ですから,治癒を目指すとともに治療後遺症をできうる限り最小限度となるような治療方針を作成します。逆に,予後不良群とは死亡率が高い群ですから,機能予後の損失よりも生命予後に重点をおいて,個々の患者において与えられる限りの初期治療をほどこします。予後中間群においての5年生存率は70%程度です。混合性胚細胞腫瘍のうち,胚腫と未熟奇形腫との混合型のみを中間群に入れて他のものは予後不良群として治療します。病理の結果の組み合わせで治療方法を細かく変えるのです。
胚腫(ジャーミノーマ)は胚細胞腫瘍の約70%を占めます。また15歳をピークとして思春期に多い腫瘍ですが10歳以下の小児にも稀ではありません。従来の標準治療は,全脳室あるいは全脳脊髄を含む領域に腫瘍線量として45〜55Gyを用いるものでした。この大量の放射線を使う治療法では,長期生存例において精神発達遅延(知能低下),間脳下垂体機能低下,放射線誘発二次腫瘍,脳主幹動脈閉塞などの遅発性放射線障害の発生が問題となりました。
胚腫は化学療法への感受性が非常に高くて,組織診断確定後に化学療法を行えば,大きなものであっても例外なく腫瘍はほぼ完全に消失します。でも,化学療法単独治療ではかなり高頻度に再発が起ってしまいます。
胚腫は一見したところ限局性腫瘍に見えますが,病理組織学的には脳室壁などにかなり広範に浸潤しているので少なくとも全脳室領域(24Gy/12分割あるいは25.2Gy14分割)に照射野を設定する必要があるということがはっきりしてきました。松谷斑の2000年のプロトコールでは,生検術で組織診断を確定した後に,カルボプラチンとエトポシドを用いる化学療法を3コース行ってから全脳室系に24Gyの低線量照射をします。追跡期間中央値5年の時点にて治療評価可能な130例において,無増悪生存割合91%,全生存割合98%という良い成績を出しています。さらにこのうち120例(86%)が完全社会復帰をしています。
胎児性癌や卵黄嚢腫など死亡率が高い予後不良群でHCG-betaあるいはAFPという腫瘍マーカーがかなりの高値を示す症例では,手術をせずにまず放射線化学療法を先行させて,腫瘍が小さくなったところで全摘出することも推奨されています。これは熊本大学にいた生塩先生が提案した治療法です。手術による播腫(転移)の誘発を防ぐという利点と,最終的には完全摘出しなければ再燃率が非常に高い予後不良群にあっての摘出術を,出血の減少と腫瘍の縮小という点において容易にするのがねらいです。松谷斑では予後不良群に,イホスファミド,シスプラチン,エトポシドを用いるICE化学療法を使用しています。
毛様細胞性星細胞腫はグレード1といわれていますから,手術で全部とってしまえば治る腫瘍のはずです。思春期の小脳にできる毛様細胞性星細胞腫の長期生存率は95%を越えていますし後遺症を残すことも少ないです。でも場所と年齢が違って,乳幼児の視床下部/視交叉にできた時には死亡率が高いし生存し得たとしても社会的に自立できる児は少ないです。
乳幼児の視床下部と視交叉に発生するものの多くは毛様類粘液性星細胞腫(pilomyxoid astrocytoma)と呼ばれるちょっと違った性質を持つものです。大きくなる速度が速くて髄腔内に播種することもあります。視床下部と両側の視路へ浸潤するために完全に摘出することができなくて,場合によっては生検術さえ危険なこともあります。放射線照射が有効ですが重篤な放射線脳障害を考えなければなりません。このような状況から最近,この腫瘍に対してはプラチナ製剤(シスプラチンもしくはカルボプラチン)とビンクリスチンを用いた併用化学療法が第一選択肢として用いられています。
この腫瘍においては数ヶ月かけて化学療法を継続することにより腫瘍縮小効果が明らかとなるので,1コースや2コースの化学療法で有効性がないと判断してはいけません。化学療法の奏効率は高くて,化学療法の開始とともに間脳症候群(ひどい痩せとか)の改善や進行性視力視野障害の停止が得られることも多いのです。私はシスプラチンとビンクリスチンの併用化学療法をまず6コース行って経過をみることにしています。経過観察中に年長児になると思春期早発症が生じることもあります。再燃時には,化学療法の再開か部分摘出か半定位的分割照射かの選択となりますが,腫瘍の残存部位と年齢を考えて決定します。逆に年長児になれば自然緩解して治癒に至る症例もあるので,治療の後の残存腫瘍の観察にはとても慎重にならなければなりません。
第1染色体短腕に欠失がある退形成性乏突起膠腫(grade 3)と退形成性乏突起星細胞腫(grade 3)に対するPCV(プロカルバジン,ロムスチン,ビンクリスチン)化学療法はとても有名な治療方法ですが,星細胞腫には効きません。小児の星細胞系腫瘍には有効な制がん剤はないといっても言い過ぎではない時代が続きました。
最近開発されたテモゾロマイドは第2世代の経口アルキル化剤で,成人の退形成性星細胞腫と膠芽腫に対して有効性が認められていますから,小児の悪性神経膠腫の治療にも期待が持たれています。
小児の治療抵抗性悪性神経膠腫と脳幹部神経膠腫に対する第2相試験が欧州で行われました。200mg/m2を5日間連続投与したものですが,残念ながら登録された55例においての客観的な奏効率は極めて低く有効性は認められないと結論されました。さらに初発例のびまん性脳幹部膠腫29例(年齢中央値6歳)に対し放射線治療後に同様なテモゾロマイドの投与を行った報告では,生存期間中央値12ヶ月で全例が死亡して,テモゾロマイドが脳幹部神経膠腫の予後を改善することはないとされました。
現在,成人と同様に放射線治療期間中に75-90mg/m2を42日間連続投与して用いる方法が検討されていますが,明らかな有効性を示唆する報告はいまだ見られません。日本でもテモゾロマイドの保険診療が認められましたが,小児脳腫瘍に対する有効性のエビデンスはなくて,また欧米の臨床試験では期待されていたような効果が否定されつつある傾向にあります。どのような小児のグリオーマに有効なのかはこれからの臨床研究を待たなければなりません。
ちなみに,成人例では第1染色体短腕欠失を認める乏突起膠腫と乏突起星細胞腫(grade 2)にテモゾロマイドの非常に高い有効性が報告され,PCV化学療法に代用し得る薬剤であるとされています。小児においても乏突起膠腫系腫瘍はテモゾロマイドに反応する神経膠腫であるのかもしれません。
多くの腫瘍型において外科摘出が予後を決定する最も重要な因子ですから,特に治療初期では脳神経外科医が果たす役割が最も大きく,外科手術の成績が予後を左右します。またいうまでもなく従来から間脳下垂体不全の治療,精神発達遅滞や症候性てんかんへの対処は小児科医に依存しています。近年では,前述のように腫瘍型によっては化学療法が重要な役割を果たすことが明らかとなってきていますから,悪性度の高い小児脳腫瘍では診断時からの小児腫瘍医の関与が重要です。
日本においての小児脳腫瘍症例は多施設に分散していて,小児脳腫瘍の治療体制と水準は望むべきレベルにはありません。小児脳腫瘍の治療を行うためには,小児の中枢神経系に造詣の深い放射線治療医と神経病理診断医の協力,眼科と耳鼻科の存在,稀少疾患治療ゆえの施設内倫理委員会の認証,保健審査と医療費対策,看護士教育,調剤の安全確保と無菌管理のための設備,多彩な予後に応じたインフォームド・コンセント,患者・家族教育と精神的支援,小児慢性疾患の迅速な手続き,家族の宿泊施設斡旋,院内学級教育,病棟内での患児と母親のストレス解消の援助など様々な対応をしなければなりません。だから地域ごとの小児脳腫瘍治療施設のセンター化が強く望まれている時代です。
上述したように全ての小児脳腫瘍は稀少腫瘍(数が少なくて珍しい)で治療方法はいちいち異なるものです。治療長期予後を慎重に考えた上での成績向上と日本においての小児脳腫瘍学の発展のためには,例外をなくして全ての症例を登録して検証する体制の整備が不可欠なのだと私は考えています。小児がん学会の努力はこれを目指してはいますが,残念ながら脳神経外科学会の中でのこの問題の認識はとても低いです。
ある米国の小児神経腫瘍医(pediatric neuro-oncologist)が,小児脳腫瘍の治療法の選択は常にcase-to-case decisionであるといった演説を聞いたことがあります。ひとりひとりの子供で違う治療を考えなくてはいけないし,まとまった治療方針で単純に治療できるものではないという意味です。残念ながらcase-to-case decisionできる経験が豊かな小児神経腫瘍医は日本にはいません。私自身も脳神経外科医としての少ない知識と経験の中で患児を治療しているのが日常ですし,日本での小児神経腫瘍医の育成を急がなければならないでしょう。
脳腫瘍は小児に発生する固形癌の中では最も頻度が高く,かつ死亡率の高い疾患です。脳腫瘍は他の臓器の腫瘍と比べて病理組織が多彩で,全ての脳腫瘍は稀少疾患(とてもまれな病気)といえます。さらに病理組織診断が同じであっても発生する部位と患者さんの年齢によって予後が変わるために治療法の選択が複雑になります。低年齢児の脳は放射線治療でとても障害を受けやすいので,化学療法が重要な治療手段となっています。髄芽腫や胚細胞腫瘍などの悪性腫瘍では脳神経外科医と小児科医の協力が欠かせません。現在日本では小児脳腫瘍の症例はたくさんの施設に分散していて,全ての子供たちに高い水準の治療ができていないこともあり,地域ごとの治療センターを確立することが望まれています。また,複雑な治療法の選択は常にcase-to-case decision(個々の患者で逐一異なること)であり,深くてレベルの高い知識をもち経験豊かな小児神経腫瘍医の育成が求められています 。
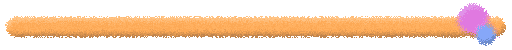
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
